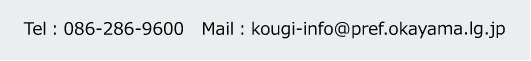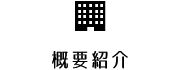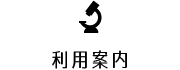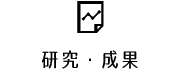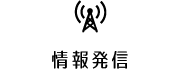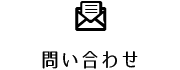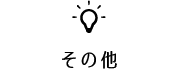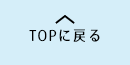本文
令和6年度研究テーマ
国等からの外部資金による研究(特別電源所在県科学技術振興事業)
窒素を活用した熱処理技術の高度化
浸窒処理温度と浸窒深さの関係に関する検討を行い、純鉄を対象とした研究では、処理温度の上昇にともない、浸窒深さが増大することを確認した。また、ステンレス鋼を対象とした研究では、低温域では表面から内部へ窒素の侵入が生じにくく、浸窒層を得るには、純鉄より高温で熱処理する必要があることを確認した。
ゴム材料の劣化に伴うナノ構造変化に関する研究
オゾン劣化により亀裂が発生したBR/EPDMブレンドゴムを原子間力顕微鏡で観察した。BR領域では深い亀裂が生成したが、EPDM領域に到達すると停止した。EPDM領域では浅い亀裂と亀裂先端の応力集中が観測された。オゾン暴露により弾性率分布が拡大したことから、伸長下での不均一な応力状態が亀裂形成の要因と推測された。また、マクロな亀裂の進展は、EPDMが亀裂の進展を阻む構造を形成することで抑制されると考えられた。
シミュレーションを用いたマルチマテリアル化と構造最適化による軽量化技術の開発
マルチマテリアル化が注目される軽量化構造材の開発手法において、カルボキシル基および水酸基を導入したPP表面を対象に、数種類の新たな官能基を導入したPP表面の分子シミュレーションを行った。その結果、アミノ基が接着強度に寄与することを明らかとした。さらにPP表面に窒素プラズマ処理を施すことで、カルボキシル基、水酸基、アミノ基を導入することができ接着強度の向上を確認した。
県単独で実施している研究
表面調整処理によるマグネシウム合金上の陽極酸化皮膜の制御および高機能化
リン酸塩陽極酸化処理したマグネシウム合金に対し、目的に応じた表面調整処理を行い、耐はく離性を有する染色技術および高い濡れ性を付与する処理技術の開発に成功した。
低伝搬損失化に向けた試作基板における電気特性等の評価
本研究では、難接着性であるポリプロピレンに銅箔を直接、熱溶着させることにより、高周波特性の優れたプリント基板を構成することができた。これは、通常のプリント基板製造では接合不能な低粗度銅箔の貼り付けが可能となったことに因る。作製基板の高周波伝搬特性に関して、ポリプロピレンを基材とすることによる伝搬損失(誘電損失)の低減効果とともに、低粗度銅箔の接合による導体損失の低減を明らかにした。
音データを用いたAIによる高精度異常検知手法の開発
畳み込みニューラルネットワークを利用して異常音の有無の判定と異常音の位置推定を行った。異常音の有無と異常音位置3点を含めた4クラス分類で67.7%の推定精度を達成した。
デニム製品の高付加価値化のための評価技術に関する研究
デニム生地を変形したときの生地の歪みを三次元スキャナを用いて詳細に解析する手法を確立した。その手法を活用し、ジーンズの膝部や太腿部を模した変形を与えた生地を解析し、それぞれの部位において、生地の歪み方が異なることを明らかにした。また、着用時を想定しデニム生地に繰り返し引張り変形を付与した試料を作製し、生地のストレッチ性への影響を調査した。
バイオマス素材の活用技術に関する研究
本研究では、セルロースナノファイバー(CNF)、およびリグノセルロースナノファイバー(LCNF)を添加した天然ゴム(NR)材料を作製し、耐候性試験を実施した。CNF未添加のNRでは顕著な色の変化や硬化劣化が確認された。CNFおよびLCNFを添加した試験片では、LCNFを添加したほうが色の変化や硬化劣化を抑制することを確認した。
企業の皆さまと共同で実施している研究
繊維製品の高付加価値化と環境負荷低減を両立した染色加工技術の確立
環境負荷低減染色加工技術の確立を目的に、精練後排水をそのまま染色工程に再利用して排水処理量削減する研究を実施した。染料凝集の原因を解明し、染料凝集を引き起こさない染色技術を確立した。共同研究企業において実機による検討を行い、数メートルサイズの生地染色技術を実用化できた。
表面特性や設計手法の高度化による新製品・新技術の開発
本研究で取り組んだ表面特性の高機能化では、短パルスレーザ利用による濡れ性向上を染色へ展開し、これまで困難であったMg合金の染色に成功した。また、レーザ加工の特長を組み合わせることで、これまでにないデザイン性が得られた。一方、設計手法の高付加価値化では、実機と同等の回路を用いた連成解析により、制御内容の事前検討に加え、高精度な損失評価も可能となった。
マルチフィジクス解析を用いたシミュレーション技術の高度化
複数の物理現象を組み合わせて考慮するマルチフィジクス解析を活用し、高精度で計算コストが低減できるモデル化法を検討した。隙間のある複雑形状の構造最適化では、食品乾燥物を対象に簡易モデルを作成し、品温と水分量が実測と概ね一致することを明らかにした。音響性能の予測では、骨格の振動を影響する吸音材料を設けた空調ダクトの音響性能を予測するモデル化法を明らかにした。
伝統的な清酒製造工程の評価と製造技術の安定化に向けた研究開発
清酒製造現場における伝統的な製造工程の各要素技術について、昨年度に引き続き特性評価と科学的検証を進めた。生もと造りの包括的な特性評価では、生もと試料からの微生物の単離同定と菌叢解析の実施、生もとに利用可能な一部の微生物(乳酸菌)候補株を選抜した。雄町を原料とした麹の特性評価では、異なる原料米で造られた麹を比較するために、試験製麹の製麹条件を決定した。槽による上槽工程の評価では、上槽途中の一般成分と香気成分について評価した。
高分子材料の診断技術の高度化に関する研究
高分子材料に関して、構造解析技術のさらなる高度化、再現・促進技術の開発、構造制御技術の開発に取り組んだ。構造解析技術では、ゴム材料を伸長下でDMA測定するための治具を設計し、測定手法を確立した。再現・促進技術では、樹脂の耐溶剤性をシミュレーションによって評価する手法を確立した。構造制御技術では、非相溶性樹脂のブレンド材料の構造を制御して衝撃強度を飛躍的に向上させ、リサイクル促進に資する成果を得た。